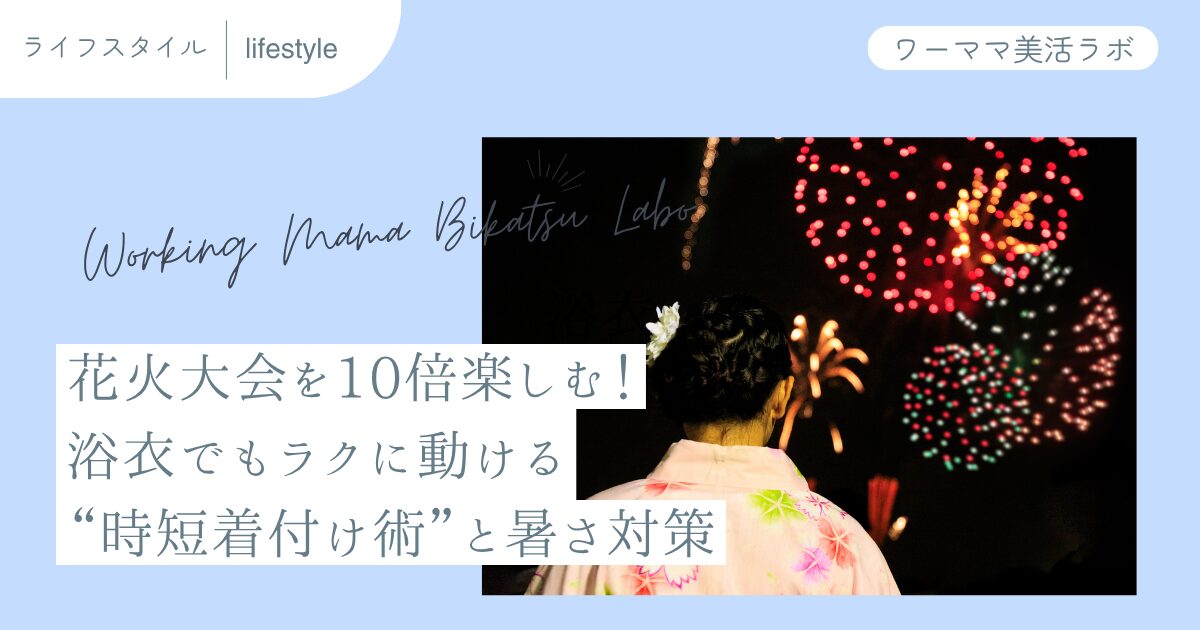「浴衣を着てみたいけど、着付けが難しそう…」「花火大会には行きたいけど、暑さが心配…」そんな方も多いですよね。
浴衣が、もっと簡単に着られたらうれしいですよね。そして少しでも涼しく着られたら。。。
この記事では、手軽に浴衣を着るコツや、花火大会で快適に過ごすポイントをわかりやすくご紹介します。
これからの季節、浴衣で快適に過ごすための準備にぜひ役立ててくださいね。

簡単にできる浴衣の着付け方法
着る前に知っておきたいルールとポイント
浴衣の着付けの前に知っておきたいルールとポイントを押さえておきましょう。
1. 「右前」で着る
浴衣は男女ともに「右前(みぎまえ)」が基本。
→ 右側の衿を体に先に当てて、左側を上に重ねます。胸元から右手が入る向きと覚えておきましょう。
2. 下着や肌着を着る
透けるのを避けるためにも、直に浴衣を着るのではなく、肌着や和装用インナーを着るのが基本。汗対策にも◎。
3. おはしょりを作る
丈を調整したら、腰で折り返してできる「おはしょり」をきれいに整えるのがポイント。
4. 衿元は「の」の字型に
衿元はの字を描くように、首元は少し抜いて着るとすっきり美しく見えます。
5. 帯の位置はウエストよりやや高めに
帯はウエスト~みぞおちあたりで結ぶと、バランスがよく見えます。

浴衣を着るときに準備するもの
浴衣を着る前に、以下のものを用意しておくとスムーズです。
- 浴衣本体
- 腰紐(コーリンベルトでもOK)
- 胸紐(あれば便利)
- 伊達締め(おはしょりが崩れないように、おはしょりの上から巻きます。)
- 帯(半幅帯が一般的ですが、兵児帯[へこおび]や作り帯なら簡単に結べます。)
- 肌襦袢、裾除けなどの着物用肌着
そのほか、帯板(帯の間に挟むアイテム)などもあると、帯にシワが寄るのを防げます。
また、最初から帯に結び目ができている、作り帯の浴衣であればさらに簡単に着られます。
初心者でも安心!浴衣の基本着付け手順
初心者でも安心して浴衣を着られるように、兵児帯を使用した基本の着付けの手順をご紹介します。
事前準備
まずは着物用の肌着を着ましょう。
着付けの流れ(兵児帯の場合)
- step1浴衣を羽織る
浴衣を羽織り、袖に腕を通します。
- step2背中の中心を合わせる
左右の衿を持ち、くるぶしが軽く隠れる高さに浴衣を持ち上げ、背中の縫い目(背中心)が体の真ん中を通るように調整します。
- step3左側を合わせる(上前)
右側を開いたまま、左側の衿を右の腰骨あたりに合わせ、たるみが出ないように調整します(仕上がりの幅をここで決めます)。
- step4右側を合わせる(下前)
一度左側を戻し、次は右側を同じように腰骨に合わせておきます。つま先を少し上げるとシルエットがきれいになります。
- step5左側を重ねる
右側はそのままに、再び左側を重ねます。右側(下前)より3〜4cm上になるようにすると、仕上がりが美しく見えます。
- step6腰紐で固定する
浴衣の位置が決まったら、腰紐でしっかり固定します。少し余裕を持たせると動きやすくなります。
- step7おはしょりを整える
わきの下の「身八つ口」から手を入れて、おはしょりを平らに整えます。真ん中から両わきへ向かってならすと自然に仕上がります。
- step8胸紐で衿を固定する
胸紐の中央をバストの下に当てて、前から後ろに回し、背中で交差させます。右わきで結び、背中のシワを伸ばしましょう(苦しくない程度に)。
- step9伊達締めで形をキープ
おはしょりが整ったら、伊達締めをお腹に当て、後ろで交差して前もしくは脇で結び、結び目を伊達締めの下へ隠します。
- step10帯を巻く
帯を体に2周巻き、前で交差させて胸の前で縛ります。片方を上にしてもう片方を下から通し、リボン結びでしっかり締めます。
- step11帯をリボン結びにする
リボンの形を整えたら、リボンが背中に来るように帯を後ろに回せば浴衣の着付けは完成です!
練習を重ねれば自然と慣れていきます。ポイントを押さえれば、初心者の方でもきれいに着こなせます。
浴衣を着る時間も、楽しんでくださいね。
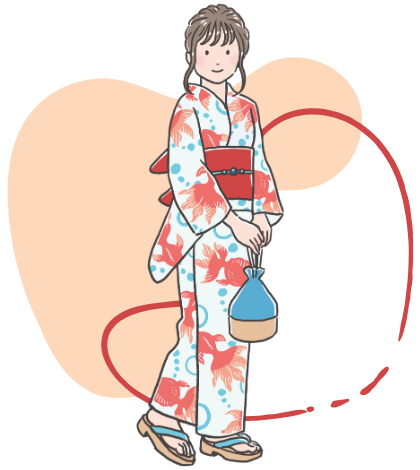
着崩れしにくいポイント
浴衣が着崩れしないためには、腰ひもや胸ひもをしっかりめに結ぶことが大切です。
ひもは苦しくない程度に、でも緩すぎないようにしましょう。おはしょりや衿元は、手で整えて形をキープするときれいが長持ちします。
座るときは裾を軽く引いてから座ると、崩れにくくなります。
また、「お手洗いに行くときどうしたら?」と不安に思う時もあるでしょう。
その際は、裾を両手でしっかり持ち上げて足元をすっきりさせましょう。帯や胸元、おはしょりが崩れたり緩まないように気をつけるのがポイントです。
ちょっとした気づかいで、浴衣姿をきれいに保てます。
花火大会をもっと楽しむための浴衣選び

気軽に楽しむ♪レンタル浴衣のすすめ
レンタル浴衣は、手軽におしゃれを楽しみたい方にぴったり。購入よりもリーズナブルで、毎年違うデザインを楽しめるのが魅力です。
「浴衣を買っても着る機会が少ないかも…」という方にも、保管の手間がいらないので安心です。
選ぶときは、まず自分の体型や身長に合うサイズをチェック。試着できるお店も多いので、実際に合わせてみるのがおすすめです。
帯や小物がセットになっていることが多く、コーディネートに悩まなくていいのも嬉しいポイント。
花火大会などのイベントシーズンは混み合うので、早めの予約が安心です。
上手にレンタルを活用して、夏のイベントをもっと楽しみましょう♪
自分らしく楽しむ浴衣コーデ
浴衣を選ぶときは、まず自分が着たい色や柄を大切に。迷ったら、身長や体型に合う柄を選ぶと、すっきり見えます。
背が高い方は縦じまや大きめの柄、小柄な方は細かい柄や横じまがよく合います。
色選びも大事なポイント。肌の色に合わせると顔まわりが明るく見えます。色白の方は淡い色、健康的な肌色の方ははっきりした色がおすすめです。
帯は浴衣との色合わせで印象が決まります。同じ系統の色でまとめると上品に、反対色だと華やかな雰囲気に。
形が作りやすい半幅帯や、簡単に結べてふんわりした印象の兵児帯も人気です。
髪飾りや帯飾りをプラスすると、より華やかになります。足元は歩きやすさを考えて、柔らかい鼻緒の下駄を選ぶと安心です。
自分にぴったりのコーディネートで、浴衣のおしゃれを楽しんでくださいね。

浴衣での熱中症対策を万全にする方法
浴衣で涼しく過ごすためのコツ
夏の花火大会など、浴衣で涼しく快適に過ごすには、浴衣の素材や着方などもポイントです。
浴衣は、通気性のよい綿や麻素材を選ぶと、汗を吸ってくれて快適です。帯は締めすぎず、少しゆとりをもたせると熱がこもりにくくなります。
肌着には襦袢を合わせると、汗を吸ってベタつきを防いでくれます。足元は通気性のある下駄や草履で、風通しよく。
「草履は足が疲れるかも?」と心配な場合は、履き慣れているサンダルでも良いでしょう。和風のデザインがあれば、浴衣にも自然になじみます。
暑さ対策アイテムの活用法
暑い日の花火大会も、ちょっとしたアイテムでぐっと快適になります。
冷却スプレーやシートは、首や脇に使うと体を手軽にクールダウンできます。ハンディ扇風機や汗拭きシート、速乾タオルがあると汗対策も安心。
日傘や扇子があると、日差し対策と涼しさアップにも役立ちます。こうしたアイテムをうまく取り入れて、浴衣姿でも涼しく過ごしましょう。
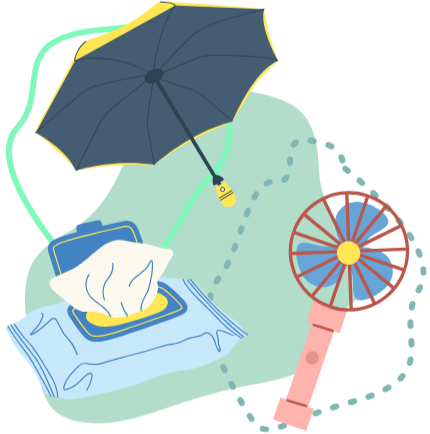
花火大会を楽しむための事前準備
花火大会への行き方と移動のコツ
花火大会を楽しく過ごすためには、会場までのアクセスを前もって確認しておくのがおすすめです。
最寄りの駅やバス停、交通の時間や混雑状況をチェックしましょう。帰りは混みやすいので、少し早めに移動すると安心です。
車で行く場合は、交通規制や駐車場の場所を調べておくとスムーズです。タクシーやレンタカーは予約しておくと安心です。
また、近くの宿に泊まれば混雑を避けて、ゆったり楽しめます。

花火大会であると便利な持ち物
花火大会を快適に楽しむために、持ち物をしっかり準備しましょう。
まずは財布や携帯、ハンカチ、ティッシュ、ウェットティッシュなどの基本アイテム。
涼しく過ごせるうちわや扇子、冷感タオルやミストスプレーもあると便利です。
虫よけスプレーは夜の虫刺され対策におすすめ。レジャーシートがあれば、地面に座るときも快適です。
急な雨に備えて、折りたたみ傘や簡易レインコートも用意しておくと安心です。
浴衣に関するQ&A
男性の浴衣ってどんなもの?
男性の浴衣は女性のものと比べてシンプルで、落ち着いた色や柄が多いのが特徴です。
男性の浴衣には、主に「角帯」が使われ、角帯は幅が広く、しっかりした素材で男らしい印象。
結び方はシンプルな「一文字結び」や「貝の口結び」が人気で、どちらも簡単でキレイに決まります。
男性の浴衣姿は、和の趣がありながらもさりげなくかっこいい印象を与えます。
浴衣と着物の違いって?
浴衣は綿や麻でできています。花火大会や夏祭りで気軽に楽しめるのが特徴です。
一方、着物は絹やウールなどで作られ、結婚式や成人式などの正式な場で着られます。種類もいろいろあって、着付けも少し難しいことが多いです。
浴衣は初心者でも簡単に着られて、着物はフォーマルなときにぴったり。どちらも和服の良さがあるので、場面に合わせて楽しんでみてくださいね。

まとめ:浴衣で過ごす花火大会は特別な時間
浴衣で過ごす花火大会は特別な時間。少しの工夫で、もっと楽しく快適になります。
自分らしいスタイルを大切にして、夏の思い出を彩ってくださいね。
新しい発見や楽しみがきっと見つかります。素敵な夏のひとときを心から応援しています。